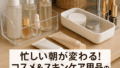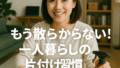コンセント周りのコードがゴチャついていて、なんだか部屋が片付かない…。
そんなふうに感じたことはありませんか?
コンセント周りのコードをすっきりまとめるテクニックを知ることで、見た目も安全性も大きく改善できます。
「どうせまた絡まるし」と諦める前に、誰でもすぐに始められる整理術を試してみませんか?
この記事では、日常生活でよくあるコードの悩みを解決するテクニックを7つ紹介したうえで、散らかった配線のリスクや、インテリアとしてもおしゃれに見せるコツもご紹介します。
さらに、100均や無印良品など、手に入りやすいアイテムもピックアップ。
読んだあとには、「えっ、コードってここまでスッキリするの?」ときっと驚くはず。
今日からできるテクニックで、部屋も気分も整えていきましょう!
コンセント周りのコードをすっきりまとめるテクニック7選
コンセント周りって、どうしてもコードがゴチャつきがちですよね。
気づいたらホコリが溜まっていたり、足に引っかかったりして危ないこともあります。
そんなときは、ちょっとした工夫で驚くほどスッキリさせることができますよ。
今回は、実用性だけじゃなく見た目にもこだわった整理術を7つご紹介していきます。
結束バンドを活用
結論から言うと、余ったコードは結束バンドでキュッとまとめるだけでもかなり見栄えが良くなります。
なぜなら、コードがバラバラになっていると絡まりやすく、見た目もだらしなくなってしまうからです。
結束バンドを使えば、コードを一定の長さに折りたたんでまとめられるので、シンプルにまとまります。
特に100均で売っているようなカラフルなものや繰り返し使えるタイプを使うと便利です。
例えば、テレビの後ろやパソコン周りって、コードが複数ある場合が多いですよね。
LANケーブルやHDMIケーブル、電源コードなどが混在していると、ひとつ外すだけでも面倒になります。
そんなとき、コードごとにまとめて結束バンドで分別しておくと、探しやすくなりますし、外観もスッキリ。
やっぱり、結束バンドは安くて手軽に使えるのが大きな魅力です。
コードの長さを調整して、美しくまとめたいなら、まずはここから始めてみてくださいね。
コード収納ボックスを使う
コンセントタップが丸見えになっていると、どうしても生活感が出てしまいます。
そんなときに便利なのが、コード収納ボックスです。
このアイテムは、電源タップごとボックスの中に収納できるので、見た目がグッとスッキリします。
コード類もボックス内で折り返してしまえば、外からはほとんど見えなくなりますよ。
たとえば、リビングにスマートスピーカーや充電ステーションを置いている人、多いんじゃないでしょうか。
その電源をひとまとめにして、ボックスに入れるだけで、かなり印象が変わります。
無印良品やニトリなどでもシンプルなデザインのものが買えるので、インテリアにも合わせやすいです。
コード収納ボックスは、見た目のスマートさと安全性、どちらも兼ね備えた優秀アイテムなんですよ。
ケーブルクリップで固定
「壁際を通すコードがブラブラして気になる」なんてこと、ありませんか?
そんなときに使えるのがケーブルクリップです。
これは、コードを固定するための小さなパーツで、デスクの端や壁に貼り付けることで配線を整えることができます。
特にスマホやタブレットの充電ケーブルなど、よく抜き差しするものにぴったり。
たとえば、寝室でスマホを充電する際、ベッド横のコードが床に落ちてしまうのって地味にストレスですよね。
ケーブルクリップで枕元のテーブルに固定しておけば、使うたびに探さなくて済みます。
さらに、デザイン性のあるクリップを使えば、インテリアのアクセントにもなりますよ。
100均でもたくさん種類が出ているので、ぜひチェックしてみてください。
スパイラルチューブで一括処理
複数のコードがぐちゃぐちゃに絡まっているときに便利なのがスパイラルチューブです。
これは、その名の通りらせん状のチューブで、コード全体を一本にまとめられる優れもの。
特にパソコン周りやテレビ裏など、複数のケーブルが集中する場所に最適です。
スパイラルチューブを巻くだけで、まるで一本の太いケーブルのように見せることができます。
「まとめてあるだけ」で掃除もしやすくなりますし、見た目も格段にスマートになります。
ブラックやホワイト、グレーなど色のバリエーションもあるので、インテリアにもなじませやすいですよ。
マジックテープでまとめる
結束バンドに似ていますが、繰り返し使いたい人にはマジックテープタイプのバンドがおすすめです。
長さが調節しやすいので、コードの太さや本数に応じて自由自在に使えます。
何度も付け外しできるから、模様替えや家電の買い替えがあっても再利用できるのがポイント。
例えばゲーム機周りって、コードの増減が激しいですよね。
そんな環境でも、マジックテープなら柔軟に対応できます。
エコでコスパも良いし、カラーを揃えると統一感も出てオシャレ感が増しますよ。
フックで壁面収納
床にコードがあると邪魔になりがち。
そんなときはコードを壁に沿わせて収納する方法もあります。
壁に貼れるタイプのフックを使えば、コードを浮かせてすっきり整理できます。
特にコンセントが中途半端な位置にあるときに便利です。
例えば冷蔵庫や電子レンジのコードを壁沿いに通すと、掃除もしやすくなりますよ。
見た目の清潔感もぐっとアップします。
粘着フックなら穴を開ける必要もないので、賃貸でも安心です。
無線化できるものは無線に
最後のテクニックはちょっと上級編。
コードを減らすなら、そもそも無線に切り替えるのも手です。
最近はワイヤレス充電器やBluetoothスピーカーなど、無線対応機器がどんどん増えています。
配線自体を減らすことで、コードの悩みから解放されるというわけです。
もちろん全部を無線にするのは難しいかもしれません。
でも、スマホの充電やイヤホン、マウスなど、切り替えやすいものから始めてみてはいかがでしょうか。
「減らす」という発想で考えると、配線整理がもっと楽になりますよ。
散らかる配線のデメリットとは?
配線って、気づけばいつの間にか絡まってゴチャゴチャしてしまいますよね。
「まあいいか」と放っておくと、見た目だけでなく安全面や生活の質にまで影響が出てしまうんです。
ここでは、コードが散らかったままだとどんな問題があるのか、4つのポイントに分けて紹介していきます。
掃除がしにくい
配線が多くて絡んでいると、掃除機やモップがうまく入らなくなってしまいます。
理由としては、床の上にコードがあることで物理的に邪魔になるからです。
コードの間にホコリがたまっても、吸い取るにはいちいち持ち上げたり、コードの間をかき分けないといけません。
例えば、テレビの裏やデスク下ってホコリの温床になりがちじゃないですか?
配線が無造作に置かれていると、掃除する気も失せますし、ホコリが絡まったコードは見た目も良くないですよね。
結局、掃除しにくい=ホコリがたまりやすい=不衛生、という悪循環につながってしまいます。
衛生的にも気持ち的にも、やっぱりスッキリさせておく方が快適ですよ。
火災や断線のリスク
実はコードがごちゃついたままだと、火災や断線といった重大なトラブルにつながる可能性があります。
理由は、コードが折れ曲がったり、他のものに押しつぶされていたりすると、内部で摩耗して断線することがあるからです。
断線した状態で使用を続けると、発熱して火災の原因になることもあります。
例えば、タコ足配線に複数の家電をつなげて、そのままホコリがたまっていたら…。
ちょっとしたショートで発火してしまうことだって十分考えられます。
見た目の問題だけでなく、安全のためにもコード整理は怠れません。
安心して暮らすためにも、配線の管理はしっかりしておきたいところです。
足を引っかけて危険
コードが床に散乱していると、つまずきやすくなって非常に危険です。
特に小さい子どもや高齢者がいる家庭では、引っかかって転倒するリスクが高くなります。
また、自分自身も忙しい朝などにコードを踏んでしまい、スマホが落ちる…なんて経験ありませんか?
たとえば、延長コードを床に這わせて使っている場面では、うっかり引っかけて抜けてしまったり、コンセントが壊れたりすることも。
こうした事故は未然に防げます。
ちょっとした工夫で、足元がすっきりするだけで安全性がグンと上がりますよ。
見た目が悪くストレスに
配線が散らかっていると、部屋全体がどこか「片付いてない印象」になります。
つまり、目に入るたびに無意識にストレスを感じてしまうんです。
なぜなら、人間の脳は「乱れているもの=不快」と認識しやすいからです。
たとえば、デスクの上が整っていると仕事がはかどるのと同じように、コードも整理されていると気持ちもすっきりします。
リラックスしたいリビングやベッドルームで、コードがぐちゃっとなっていると、ちょっと気になってしまいますよね。
逆に配線がきれいにまとめられていると、「部屋全体が洗練されて見える」から不思議です。
見た目の整頓は、心の整頓でもあるんですよ。
おしゃれにまとめるインテリア術
配線って、実用的にまとめるだけじゃなく、おしゃれに見せる工夫もできるんですよね。
せっかくなら、生活感を隠しつつインテリアとしても楽しめるようにしたいところ。
ここでは、見た目にこだわりたい方のために、スタイリッシュで実践しやすいアイデアを紹介していきます。
木箱やカゴで隠す
まずおすすめしたいのが、コード類を木箱やカゴの中にまとめて収納する方法です。
なぜなら、むき出しのコードってそれだけで生活感が出てしまうからです。
でも、ナチュラルな素材の木箱や布製のカゴにまとめれば、部屋の雰囲気を壊さずに済みます。
たとえば、Wi-Fiルーターの電源やUSB充電器など、見た目がちょっと気になるガジェット周り。
これをひとまとめにして木箱に入れれば、ナチュラルインテリアや北欧風の部屋にもスッと馴染みますよ。
フタ付きのカゴならホコリも入りにくいので、掃除の手間も減らせますし、見た目も断然スマートになります。
インテリアに馴染む色を選ぶ
コードや収納グッズの色を部屋のインテリアに合わせて統一するだけで、グッとおしゃれに見えます。
理由としては、色のトーンが揃っていると、視覚的なノイズが減って空間がすっきりして見えるからです。
特に白や黒、グレーなどのベーシックカラーを選べば、どんなインテリアにも自然と溶け込みます。
例えば、白を基調としたお部屋なら、黒いコードが目立ちやすいですが、白い延長コードに替えるだけで印象が変わります。
反対に、木目調の家具が多い部屋なら、ベージュ系やブラウンのコードカバーを使うと馴染みやすいですね。
ちょっとした色選びの工夫で、部屋全体の統一感が高まり、洗練された印象になりますよ。
コード収納付き家具を使う
最近では、コード収納を考慮した家具も増えてきています。
こうした家具を選ぶだけで、配線整理がぐっとラクになります。
たとえば、テレビボードにケーブル通し穴があるものや、コンセント付きのサイドテーブルなど。
これらを使えば、配線を家具の裏側に隠しつつ、必要な場所に電源を確保できます。
ベッド横に置くナイトテーブルでも、引き出しの中に配線穴があるタイプなら、スマホ充電しながら見た目もすっきり保てますよね。
一石二鳥のアイテムとして、ぜひ家具選びの際には「配線整理がしやすいか?」もチェックポイントにしてみてください。
DIYで隠し配線に挑戦
ちょっと上級者向けにはなりますが、自分で壁や家具の裏にコードを通す「隠し配線DIY」もおすすめです。
なぜこの方法がいいかというと、見た目がとにかくスッキリするからです。
コードが表に出ないだけで、「ここ本当に家電あるの?」と思うくらい空間が整います。
たとえば、モールという配線カバーを壁に貼り付けて、その中にコードを通すだけでも効果抜群。
ペンキで壁と同じ色に塗れば、さらに目立たなくなります。
また、家具の背面にフックをつけて配線を這わせるだけでも、コードが床に垂れず、整った印象になりますよ。
自分の部屋のスタイルやレイアウトに合わせて自由に工夫できるのが、DIYの魅力ですね。
ちょっと手間はかかりますが、その分オリジナル感のある仕上がりになるので、満足度はたかくなります。
100均・無印で手に入るおすすめアイテム
「コード整理ってお金かかりそう…」と思っている方に朗報です。
実は、100均や無印良品には優秀なコード整理アイテムがたくさん揃っているんです。
しかもどれもリーズナブルで、見た目もシンプルなので、気軽に取り入れやすいのが魅力ですよ。
ダイソーの配線カバー
まずおすすめなのが、ダイソーで手に入る配線カバーです。
これは、壁や床に沿ってコードを隠すためのアイテムで、簡単に設置できるのがポイント。
なぜこれが便利かというと、見た目が整うだけじゃなく、コードを踏んだり引っかけたりする心配も減らせるからなんです。
しかも両面テープ付きのものもあるので、工具不要で誰でもすぐに使えます。
たとえば、冷蔵庫の裏から出た電源コードを床に沿わせて、リビングのコンセントに向かって配線したい場合。
この配線カバーを使えば、床にぴったり密着させて目立たずに通すことができます。
カラーも白やグレーなど部屋に馴染みやすい色が多く、初心者にもぴったりですよ。
セリアのコードクリップ
次にご紹介するのは、セリアのコードクリップです。
机の裏や壁などに取り付けて、コードを固定するための便利グッズですね。
このクリップが優秀なのは、粘着式でどこにでも貼れること。
しかもデザインがシンプルなので、目立たずインテリアを損ねません。
たとえば、スマホの充電コードが床に落ちて毎回拾うのが面倒なとき。
クリップを机のフチに貼り付けて、そこにコードを通しておくだけで、使いたいときにサッと手に取れます。
「ちょっとしたストレス」を取り除いてくれる、まさに名脇役です。
無印のケーブル収納ボックス
コードを“隠す”ための収納として絶大な人気を誇るのが、無印良品のケーブル収納ボックスです。
見た目はとにかくシンプルで美しく、どんな部屋にもなじむデザインが特徴。
このアイテムが便利な理由は、延長コードやタップごと収納できる大容量設計にあります。
さらに、上部にスリットがあるため、スマホを置いてそのまま充電することも可能。
たとえば、リビングのテレビ周辺や、寝室のベッドサイド。
コード類が一箇所に集まる場所に設置すれば、それだけで空間がすっきりします。
少しお値段は張りますが、その分の価値は十分あるアイテムですよ。
キャンドゥの配線隠しシール
最後に紹介するのは、キャンドゥで見つかる配線隠しシールです。
こちらは、壁の色に近いカラーのシールでコードの上から貼り付け、視覚的に目立たなくするグッズ。
この方法の良さは、コードを隠すというより“溶け込ませる”発想にあるんですよね。
配線カバーよりも軽やかで、部屋の壁に自然になじむのがポイントです。
たとえば、壁にテレビを取り付けたときに下にコードが垂れてしまっている状態。
この配線隠しシールを使えば、コードの存在感がほとんど気にならなくなります。
賃貸でも使えるアイデアとして人気があり、誰でも簡単に取り入れられるアイテムです。
まとめ
コンセント周りのコードは、工夫ひとつで見違えるほどスッキリ整理できます。
結束バンドや収納ボックス、ケーブルクリップなどの基本アイテムから、スパイラルチューブや無線化といった上級テクニックまで、使い方次第で配線の悩みはぐっと軽減されます。
また、散らかったコードは見た目が悪いだけでなく、掃除の手間や火災のリスク、転倒の危険性など、多くのデメリットも引き起こします。
整理することは、快適な暮らしと安全を守るための大切なステップでもあるんです。
さらに、インテリアに馴染む工夫や、100均・無印良品の便利アイテムを活用すれば、手軽に始められるのも魅力。
日々のストレスを減らし、心地よい空間をつくる第一歩として、今回紹介したテクニックをぜひ取り入れてみてください。