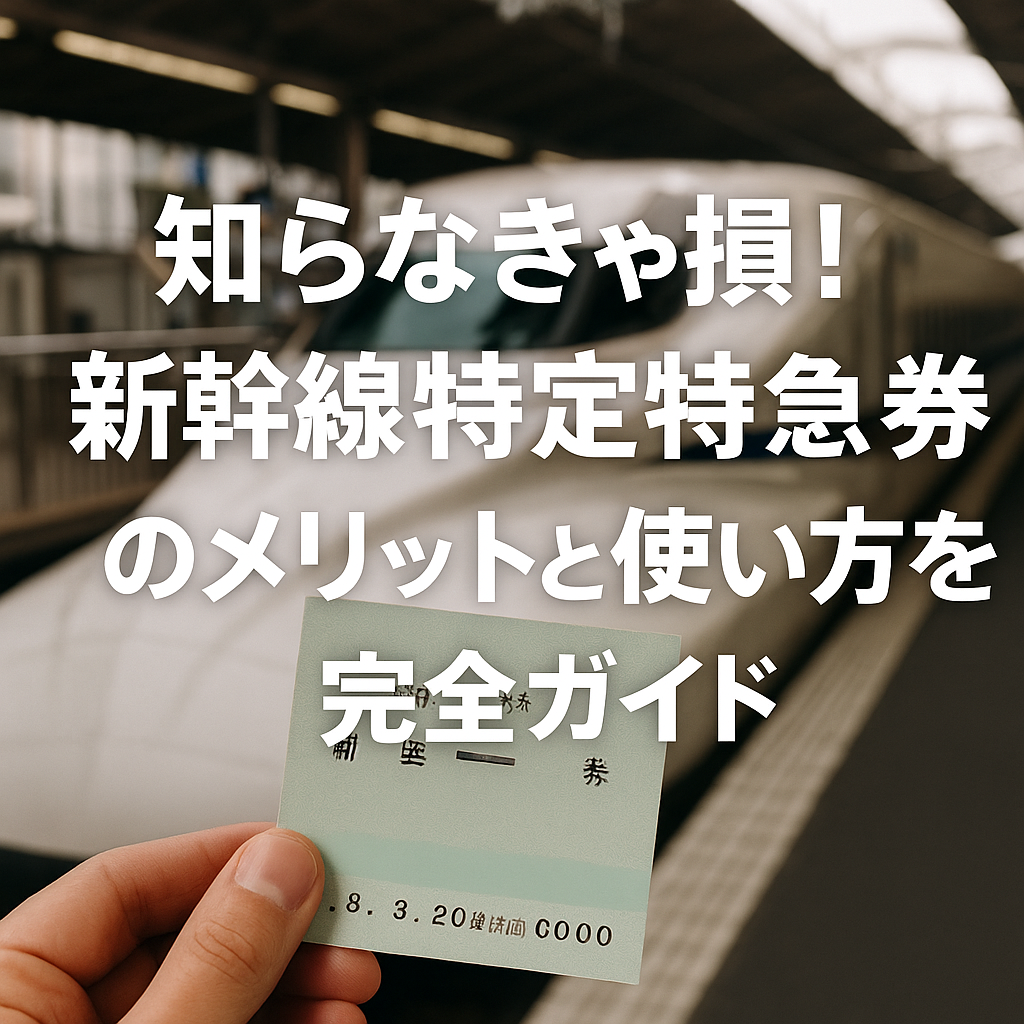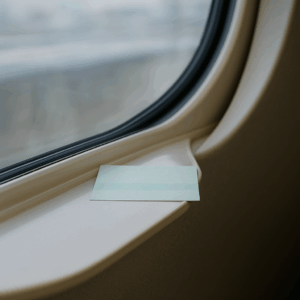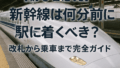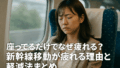「新幹線特定特急券って何?」「通常の特急券とどう違うの?」そんな疑問を感じたあなたに向けて、この記事では特徴やメリット、注意点まで徹底解説します。
出張・通学・旅行…短距離移動が多い人ほど、この特急券の魅力は必見です。
知っておくだけで、移動の選択肢がぐっと広がりますよ。
新幹線特定特急券とは何かを徹底解説

普通の特急券との違い
新幹線特定特急券と聞いて、まず「普通の特急券とどう違うの?」って疑問に思いますよね。
一言でいうと、「特定区間のみで使える、自由席限定のお得な特急券」です。
通常の新幹線特急券は、どの区間でも指定席でも利用できますが、特定特急券はJRが定めたごく一部の短距離区間に限られていて、自由席専用なんです。
例えば、東京〜小田原や新大阪〜京都など、移動距離が短いけど新幹線を使うと便利な区間に設定されています。
こうした区間では、在来線よりも新幹線の方が断然速くて快適ですが、そのぶん料金が気になりますよね。
そこで登場するのがこの特定特急券。普通の特急券よりも価格がグッと抑えられているため、コスパ重視の方にはぴったりなんです。
この違いを知っているだけでも、移動手段の選択肢がぐっと広がりますよ。
「同じ新幹線に乗るのに、どうして料金が安いの?」と疑問に思うかもしれませんが、それは利用区間が限定されていることと、指定席が使えないという条件があるからなんですね。
なので、「指定席じゃなくてもいいから、ちょっと早く移動したい!」という人には、まさにうってつけの切符なんです。
購入できる場所と方法
新幹線特定特急券は、どこで買えるのか気になりますよね。
結論から言うと、「JRの駅のみどりの窓口」「指定席券売機」「一部の旅行会社窓口」などで購入できます。
ただし、インターネット予約サービス「えきねっと」や「EX予約」では原則取り扱っていないので、ネットで完結させたい人にはちょっと不便かもしれません。
一番確実なのは、駅にある「指定席券売機」を使う方法です。
券売機のメニューで「自由席特急券」や「区間を指定した特急券」などを選ぶと、対象区間なら自動的に特定特急券が発券される仕組みになっています。
例えば、東京駅で「東京〜小田原」の自由席特急券を購入しようとすると、自動的に特定特急券の料金が適用されるんです。
窓口でも「特定特急券をください」と伝える必要はありません。
「東京〜小田原の自由席で」と言えば、窓口の駅員さんが該当する切符を出してくれますよ。
また、ICカード乗車では利用できない点にも注意が必要です。
たとえば「Suicaで乗って、あとから清算すればいいや」という考えは通用しません。
紙のきっぷとして、事前に購入しておく必要があります。
忙しい朝などは、ちょっとした並び時間も気になると思いますので、券売機でのスムーズな購入がおすすめです。
この券は「乗車直前まで購入可能」なので、計画的でなくても気軽に使えるのが便利なポイントですね。
使える区間の特徴
新幹線特定特急券が使える区間は、実はかなり限られています。
JRが「特定」として指定した短距離区間のみに使える特別な券なんですね。
たとえば、代表的な区間としては以下のようなものがあります。
-
東京〜小田原(東海道新幹線)
-
新大阪〜京都(山陽新幹線)
-
博多〜小倉(九州新幹線)
これらの区間の特徴は「在来線だとそこそこ時間がかかるけど、新幹線を使うとすごく早い」という点です。
たとえば、東京〜小田原は在来線の東海道線だと1時間以上かかるのに対し、新幹線ならわずか30分程度で到着できます。
時間をお金で買う感覚に近いですよね。
しかも、その「お金」も通常の新幹線特急券よりグッと安いわけですから、これは使わない手はありません。
もうひとつ大事なのが、これらの特定区間は「自由席専用」であること。
自由席のある「こだま」や「ひかり」「さくら」といった列車での利用が前提になっています。
「のぞみ」や「みずほ」などの全席指定の列車では、特定特急券は使えません。
また、同じ区間でも日によって運転される列車の種類が変わることもあるので、事前に運行状況を調べておくと安心です。
こうした「短距離だけどニーズが高い」区間が対象になる背景には、混雑緩和や利便性向上といった鉄道会社側の戦略もあるんですよ。
知らないと損する、でも知っていればとても賢い選択になる、それが新幹線特定特急券の最大の魅力なんです。
対象となる車両と座席
新幹線特定特急券を使ううえで、「どの車両に乗れるのか?」っていうのもかなり重要ですよね。
まず大前提として、この特急券は自由席限定です。
つまり、指定席やグリーン車には乗れません。
対象となるのは、主に「こだま」「ひかり」「さくら」「つばめ」など、自由席の設定がある列車です。
たとえば、東京〜小田原なら「こだま」、新大阪〜京都なら「ひかり」や「こだま」、博多〜小倉なら「つばめ」といった具合です。
「のぞみ」や「みずほ」などの全席指定列車では、そもそも自由席がないので、特定特急券では乗車できないんです。
また、自由席の車両がどこにあるのかは、駅の電光掲示板や案内図に「自由席は1〜3号車」などと書いてあるので、それを確認して乗車するようにしてくださいね。
自由席なので「空いてる席に座ってOK」ではあるんですが、特に通勤時間帯や週末はけっこう混雑します。
「満席で立ちっぱなし」なんてこともあるので、できれば発車15分前くらいにはホームに並んでおくと安心です。
ちなみに、車両そのものは通常の新幹線とまったく同じなので、座席のクッション性や快適さは変わりません。
短距離でも「在来線と比べて移動が快適なのがいい!」と感じる人は多いですね。
まとめると、「自由席限定で、対象の短距離区間に設定された列車」であれば、この券が使えるということです。
この条件を理解しておけば、券を買ってから「乗れなかった…」なんて失敗はしませんよ。
新幹線特定特急券のメリット5つ

運賃が安くなる
新幹線特定特急券の最大のメリット、それはやっぱり「運賃の安さ」です。
通常の特急券に比べて、200円〜500円ほど安く設定されていることが多く、短距離であればあるほどお得感が強くなります。
たとえば、新大阪〜京都間であれば、在来線だと560円、新幹線自由席だと1,420円程度ですが、特定特急券なら1,000円前後で乗れることも。
この価格差は、ちょっと贅沢に見えても実はかなりリーズナブルなんです。
忙しい朝や、天気の悪い日なんかに「たった数百円で快適さと時短を買える」って考えたら、全然アリですよね。
しかも、価格があらかじめ設定されていてブレが少ないので、「今日は高くなってる!」みたいなことも起きません。
短距離で賢く移動したい人にとっては、まさに最強の選択肢といえます。
自由席が使える
新幹線特定特急券の嬉しいポイントのひとつが、「自由席をそのまま使える」という点です。
通常の新幹線では、指定席をとるには追加料金がかかりますよね。
でも、特定特急券はそもそも「自由席専用」として設計されているので、自由席であれば追加費用なしでそのまま乗車できるんです。
「え、自由席って混んでるんじゃないの?」って思うかもしれませんが、実際は短距離区間なので乗車時間も短く、満席になりづらいんですよ。
特に午前中の遅い時間帯や、午後の早めなどは意外と空いていて快適に移動できます。
また、自由席なら「急に予定が変わったとき」や「指定時間に間に合わなかったとき」でも柔軟に対応できますよね。
たとえば、「急いで移動したいけど、何時の列車に乗れるかわからない」ってときに、この自由さがとても助かります。
もちろん、乗りたい列車に自由席があるかどうかは事前に確認しておくと安心です。
駅の掲示板やJRの公式サイトで「〇号車が自由席」と表示されていますから、それを見て乗車位置を決めてください。
新幹線の自由席って、実はけっこう快適で座席もふかふか。
在来線の普通車よりもリクライニングがしっかりしていて、短時間でもリラックスできますよ。
つまり、特定特急券は「おトクに乗れて、しかも席もちゃんとある」っていう、コスパ最高な選択肢なんです。